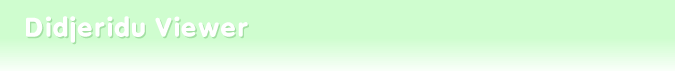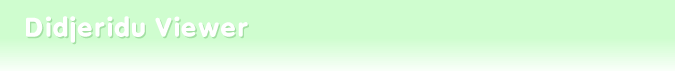|
70年代のDavid Blanasi作と思われるMago。使用感があり、マウスピースはジョイントされている。
2001年にMagoを作るためにブッシュに入ったDavidは、そのままブッシュの中へ姿を消した。それ以来、Davidの作品は新たに作られる事はない。今までいくつも彼の作品は見てきた。その多くは、90年代に主に販売用として作っていた楽器で、それらの楽器を自分が演奏してみても、なぜかそれほどピンっとくることはなかった。
吹いてみても「あのサウンド」に鳴らないからだ。もちろん自分の演奏技術の低さがあることは言うまでもないが、それにしてもどうもかけ離れているように思えた。そのため、「一体David Blanasiはどんな楽器を自分の演奏用に使っていたんだろうか?」という疑問と、今まで目にしてきた楽器は彼の演奏クオリティなんだろうかという疑問がその後の僕の頭の片隅にはいつもあった。
そんな中一冊の本と出会う事になる。ダーウィンのチャールズ・ダーウィン大学の図書館でアボリジナル関係の書籍を閲覧していたら、Jennifer Isaacsの書いた『Australian Aboriginal Music』という1979年出版の本を見つけた。いきなり表紙には、Djoli LaiwangaとDavid Blanasi。裏表紙にはダンサーのDavid Gulpilil。三人とも丁寧に描かれたボディ・ペインティングと鳥の羽やヒモで作った腕輪やコシミノなどを身にまとっている。そこで使われていた楽器がこのMagoがこの楽器とペイントのスタイルが非常に似通ったものだった。
以来、そのMagoに似た形状とペイントのものを探し続けてきたが、なかなか出会う事はできなかった。そんな中出会ったのがこのMagoだ。最初に吹いた時に、パッと「あのサウンド」が鳴った。しかも非常に使用感があり、使いこまれている。David Blanasiの使用Magoというのはかつて出会った事がない。
この楽器の最も特徴的なのはマウスピースがジョイントされているという事。かなり大きな吹き口に適度な大きさの木のわっかを埋め込み、隙間をシュガーバグの蜜鑞でうめるというアーネム・ランドで伝統的に行われる手法でマウスピースが作られているのだ(写真を参照)。
この太い楽器は1.8kgと非常に軽量で、厚みは均等に薄めに削られている。内部の空洞はボトムから上へ40cmほどが丁寧に削れており、それ以外はナチュラルな状態で美しく滑らかな表面になっている。写真でみどりがかったような色に見える部分は、炭をつかった黒で、古くなって独特の雰囲気をかもしだしている。描かれているのはカンガルーの頭をしたレインボーサーペント(?)と人、そして魚とヘビなど。
描かれているテーマと手法は、ダーウィン博物館に展示されているDavid Blanasiの樹皮画とかなり似通っている。そして何よりもクロスハッチの線の細さにDavidらしさを感じる。またペイントの向きがボトムを上にした状態というのもユニークな点だ。
音質は中低音〜高音までまとまりがあり、60年代に録音された名盤『Arnhem Land Popular Classics』で聞かれるDavidの演奏のような質感がある。ただ無数のクラックがあり、そこから空気もれがあるため、演奏感はもっと良いだろう。もしクラックを補修したら、ピッチは少し上がるだろう。
この楽器の現状はすでに演奏に耐えうるものではなく、ミュージアム・クラスの域に達しているが、この楽器を一つのサンプルとして西部アーネム・ランドの楽器を探すきっかけになればいいなと思う。
|